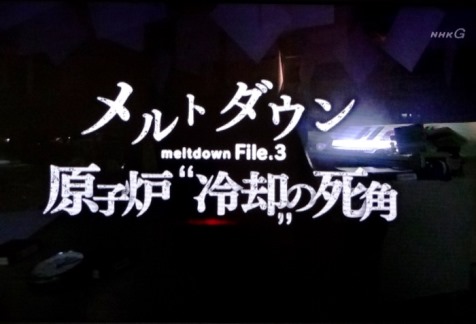
2年前の3月11日、巨大津波に襲われた福島第一原発は、高温の核燃料棒が溶け出す「メルトダウン」を起こして、12日 午後3時36分に1号機が水素爆発を起こしました。今回検証された一つ目は、この1号機に備わっていた冷却装置イソコン(アイソレーション コンデンサー)が正しく作動していればメルトダウンを防げたのではないかということです。なぜならばイソコンは電気に頼らずに原子炉内の水を冷却することができる装置だからです。
地震発生後、原子炉内では制御棒が核燃料棒の間に挿入され核分裂の連鎖を停止しますが、300度という高い温度のままの原子炉を冷却しなければ、核燃料はメルトダウンして制御できなくなってしまいます。1号機・2号機の間にある中央制御室では、イソコンを使って1号機の原子炉の冷却をはじめました。原子炉は急激に冷却をすると傷むため、イソコンの起動と停止を繰り返しながら冷却を行ないます。しかし、大津波による海水流入で11日 午後3時37分に全交流電源を喪失し、1号機・2号機の動作状況を確認できなくなりました。中央制御室から350メートル離れた免震重要棟では、この時イソコンが動いているという誤った認識がされていたのです。2号機の冷却装置であるRCICという冷却装置は、運転を電気で調整する複雑な機械だったため、免震重要棟は2号機の冷却ができていないことの方に不安を感じていました。
NHKは取材を通して、イソコンが動いていないことに気付くチャンスが何度かあったのに、それを生かせなかった問題点を指摘しました。全電源喪失の1時間後(午後4時44分)、“ブタの鼻”と呼ばれるイソコンから発生する蒸気を建屋の外に排出する管から蒸気が「モヤモヤ出ている」ことが確認され、免震重要棟はそれをイソコンが動いている状態と誤認したのです。アメリカのナイン・マイル・ポイント原発では、4年に一度イソコンの起動試験を行なっていて、イソコンが作動している時に出る蒸気の激しさを作業員は知っていました。それに対して福島第一原発では、イソコンを40年も動かしたことがなかったのです。
二つ目に検証された問題は、3号機の消防車による注水冷却の失敗です。3号機は1号機と違って非常用バッテリーで冷却装置が動いていましたが、それも時間の問題でした。消防車を使って外部から注水を行なうために、複雑な配管のバルブを操作して、早く確実に水を注がないとメルトダウンしてしまいます。しかし、そうした訓練は一度もしたことがなかったのです。13日午前9時25分から注水を開始し、その日だけで400トンを超える水が注入されましたが、実は抜け道を通って復水器という場所に流れ込んでいたのです。復水器への抜け道にはポンプがあり、そのポンプが動いていれば水は流れないはずでした。全電源喪失を想定していなかったためにこの抜け道が見落とされていたのです。そのために3号機もメルトダウンして、14日午前11時1分に水素爆発しました。
今回のNHKスペシャルで検証された問題でさえも、国と原子力規制委員会は充分な対策を立てておらず、地震と津波によって生じる原発の過酷事故を確実に防ぐ手だては今のところありません。福島第一原発の廃炉作業さえも大量の汚染水の処理に行き詰まっています。原発の安全性について国民が納得できるものは何もありません。直ちに「原発ゼロ」を実現し安全な自然循環型エネルギーの開発をすすめるべきだと私は思います。
